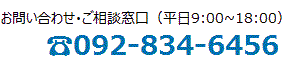法人成りをご検討の方へ FOR PRESIDENT
個人事業を法人化することには以下のメリット・デメリットがあります。しかし、今後事業を拡大していこうと考えられている事業主様は、細かいことは気にせず法人化するというのも一つの手ではないかと考えております。事業のミッションは永続したビジネスの継続、これには法人という器が一番適していると考えるからです。
税務的な観点から言えば、現在の税制の大きな流れは個人増税、法人減税であり、この方向性はもはや後戻りはしないと考えられます。となれば、この時代の税務戦略はマクロ的には法人成りといえるのですが、ミクロ的にも個々の事業主様の実情に合わせ、あらゆる角度からフォーカスを当て法人成りのシミュレーションを行い、また法人成りについて事業主様が考えられているハードルなどについてディスカッションさせていただきます。
ご相談・ディスカッションは無料です。

法人成りのメリット・デメリット
- メリット
・役員給与を支給した場合の給与所得控除の活用
・新規に法人を設立した場合の2年間の消費税の納税免除
・生命保険を活用した節税・蓄財
・役員退職金の支給
・決算月の選択
・福利厚生費の有効活用(宿泊日当等の旅費)
・繰越欠損金の有効活用
・外部信用力の向上
- デメリット
・地方税均等割の増加
・法人設立費用の負担
・税理士などの専門家報酬の増加
・社会保険の強制加入
・交際費の損金算入額の制限
- 各メリットの詳細
① 役員給与を支給した場合の給与所得控除の活用
個人事業主の場合は売上から経費を差し引いた事業所得が代表者に対する実質的な給与となっていましたが、法人成り後は法人からの役員報酬額が給与収入となり、一定の給与所得控除を控除した後の所得が代表者個人の給与所得となります。
ただし、法人成り後は個人の事業所得に認められていた65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。
② 新規に法人を設立した場合の二年間の消費税の納税免除
新設法人が一定の要件を満たした場合は、法人設立後2年間は消費税の納税が免除されます。
具体的には、
・資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月の期間における課税売上高又は給与等の合計額が1,000万円以下であること
が要件となります。
③ 生命保険料を法人が支払った場合の法人の経費の計上
個人事業主の場合の生命保険料の支払いは所得控除としてしか活用できず、その限度額も最大で12万円に制限されていますが、代表者の退職金を目的とする逓増定期保険などについては保険料支払額の1/2を税務上の経費にできます。
④ 事業主自身への退職金の支給
個人事業主においては代表者に対する退職金の支給は不可能ですが、法人設立後は退職金を支給することができるようになります。
退職金を受け取った場合は、退職所得控除を活用でき、また、その退職所得控除を控除した後の金額を1/2にして所得税を計算できます。
⑤ 決算月の選択
個人事業においての事業年度はその年の1月1日から12月31日であり、申告期限も所得税は3月15日、消費税は3月31日となっていますが、法人の場合は事業年度は定款で自由に決めることができます。
したがって、個人事業だと繁忙期と決算時期が重なった場合、税務対策が行えなかったといったケースもでてきますが、法人の場合は繁忙期を避けた時期に決算期を設定することで余裕をもって税務対策を行えます。
⑥ 福利厚生費の有効活用(宿泊日当等の旅費)
法人の場合には、旅費規程により宿泊日当、営業日当等の経費の計上が可能になります。
また、その支給された日当は社会通念上不相当な額でなければ所得税の計算上非課税所得となりますので、日当に対して所得税は課税されません。
⑦ 繰越欠損金の有効活用
所得税の場合の繰越損失の繰越をできる期間は3年間ですが、法人の場合は9年間損失を繰越して翌事業年度以後の利益と通算することができます。
- 各デメリットの詳細
① 地方税均等割の増加
個人事業の場合の住民税の均等割は福岡市・福岡県の合計で4,500円ですが、法人になると最低でも福岡県と福岡市の合計で71,000円になります。
② 法人設立費用の負担
法人を設立する場合は、法人の登記に要する税金などで30万円近くの費用がかかります。
③ 税理士などの専門家報酬の増加
法人設立後は法人運営を万全なものとするために税理士・社会保険労務士等専門家の協力が必要不可欠ですので、その分のコストが増加します。
④ 社会保険の強制加入
個人事業においては従業員が5名未満の場合は社会保険の加入は任意ですが、法人設立後は社会保険には強制的に加入しなければなりません。
その分の法人の負担額は人件費の約14%ほどになります。
したがいまして、新たに従業員を雇う場合や役員報酬を決定する場合は常にこの社会保険の負担を意識する必要があります。
⑤ 交際費の経費否認
個人事業においては事業を行う上で必要な交際費は全額が経費となりましたが、法人の場合はその経費算入に一定の制限がかかります。
大会社以外の場合ですと、具体的には支出した交際費が年間600万円までは支出した額の90%が税務上の経費として認められ、残りの10%と年間600万円をオーバーした部分は税務上の経費として認められません。
(参考)会社設立(法人成り)にかかる費用
| 項目 | 電子定款 | 紙の定款 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
| 印紙代 | 0円 | 40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
| 合計 | 202,000円 | 242,000円 |
通常、会社設立を専門家に依頼すると手数料を要しますが、税務顧問を弊税理士法人にご依頼いただける場合には、会社設立に伴う手数料は通常料金よりも安い50,000円しかいただいておりません。また、電子定款にて会社設立の手続をすすめることができますので、手数料込みで252,000円と会社設立に伴う初期費用を低く抑えることができます(税務顧問契約をされない場合は80,000円となります。)
ご自身で手続きをされた場合と10,000円しか変わらず、かつ、何もご自身で手続きをする必要がないことを考えると、専門家にご依頼することをおすすめいたします。
法人成り(会社設立)Q&A
![]() 会社といえば株式会社と有限会社が思いつくのですが、他にもあるのですか?
会社といえば株式会社と有限会社が思いつくのですが、他にもあるのですか?
現在では新規に会社を設立する場合は株式会社以外には持分会社である合同会社・合資会社・合名会社の4種類がありますが、対外的な信用力や資本の集めやすさを考えると、一般的には株式会社の設立が一般的です。
![]() 自分が設立した会社の株式は他の人に渡したくないのですが、株式の譲渡に制限をかけられますか?
自分が設立した会社の株式は他の人に渡したくないのですが、株式の譲渡に制限をかけられますか?
この場合、会社の承認がなければ株式を譲渡することはできません。
![]() 自分一人で会社を設立しようと思うのですが、株主と社長は兼ねることができますか?
自分一人で会社を設立しようと思うのですが、株主と社長は兼ねることができますか?
ちなみに社長や会長といった役職名は会社が任意に使用している言い方で、会社法で定める役員は取締役と監査役と会計参与になります。
![]() 取締役には任期はあるのでしょうか。
取締役には任期はあるのでしょうか。
![]() 会社はどのようにしたら設立したことになるのでしょうか。
会社はどのようにしたら設立したことになるのでしょうか。
その中には絶対的に記載しなければならない事項と会社が選択した場合に限り記載する事項があります。
![]() 登記をすればどのような業種でも事業を始められるのでしょうか。
登記をすればどのような業種でも事業を始められるのでしょうか。
![]() 資本金はどのようにして集めるのでしょうか。
資本金はどのようにして集めるのでしょうか。
一般的に小規模な会社を設立する場合は発起設立になります。
また、発起人は一人でも構わないので、発起人=株主が一人の会社も設立可能です。
![]() 定款とは何ですか?必ず作成して従う必要があるのでしょうか?
定款とは何ですか?必ず作成して従う必要があるのでしょうか?
![]() 定款には何を記載するのですか。
定款には何を記載するのですか。
![]() 現金以外を出資しようと思うのですが、問題ありませんか?
現金以外を出資しようと思うのですが、問題ありませんか?
ちなみにこの場合の価格は出資する財産の現在の価格になります。また、出資価格次第では出資した人に税負担が発生する可能性があるので現物を出資する場合には注意が必要です。
![]() 定款の認証が終わり、資本金も払い込み登記が完了しました。その他に行政手続きはありますか?
定款の認証が終わり、資本金も払い込み登記が完了しました。その他に行政手続きはありますか?
①国税
1.法人設立届
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
②地方税
1.法人設立届出書(県税事務所)
2.法人設立届出書(市町村役場)
③社会保険
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
このほか、従業員を雇った場合は労働保険の手続きも必要になります。
これらの書類を提出する場合は必ず同じ書類をもう一部控え用として作成し、役所から控え用に受け取り印をもらうようにすることが余計なトラブルを避けるコツです。
![]() 消費税の還付を受けられることがあると聞いたのですが。
消費税の還付を受けられることがあると聞いたのですが。
ただし、還付を受ける場合には
1.課税事業者であること
2.簡易課税制度を選択していないこと
の要件を満たす必要があります。
資本金が1,000万円未満の場合は何も手続をしなければ原則的に免税事業者になりますが、大きな設備投資が見込まれる場合はあえて課税事業者を選択すると消費税の還付を受けられます。
課税事業者を選択する場合には課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署に提出します。
その提出期限は設立一年目の法人は設立事業年度末日、それ以外の法人は課税事業者になろうと思う年度の初日の前日です。
この選択をした場合には二年間は消費税の課税事業者であることが強制されますので、二年間を通算して還付額の方が納税額よりも多ければ課税事業者を選択した方が有利になります。
一度課税事業者選択届出書を提出した後に免税事業者に戻りたい場合は課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ免税事業者に戻れませんので注意が必要です。
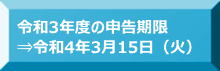
※確定申告はご依頼の内容によっては、時間を要するケースがあります。申告期限ぎりぎりのご依頼はお断りさせていただくことがございますので、お早めにご相談ください。

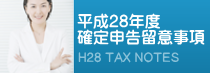

サイト運営グループ
【税務部門】
![]()
(福岡オフィス)
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号 北山興産ビル3F
(福岡中央オフィス)
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲビル314号
【アドバイザリー部門】
![]()
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲビル314号